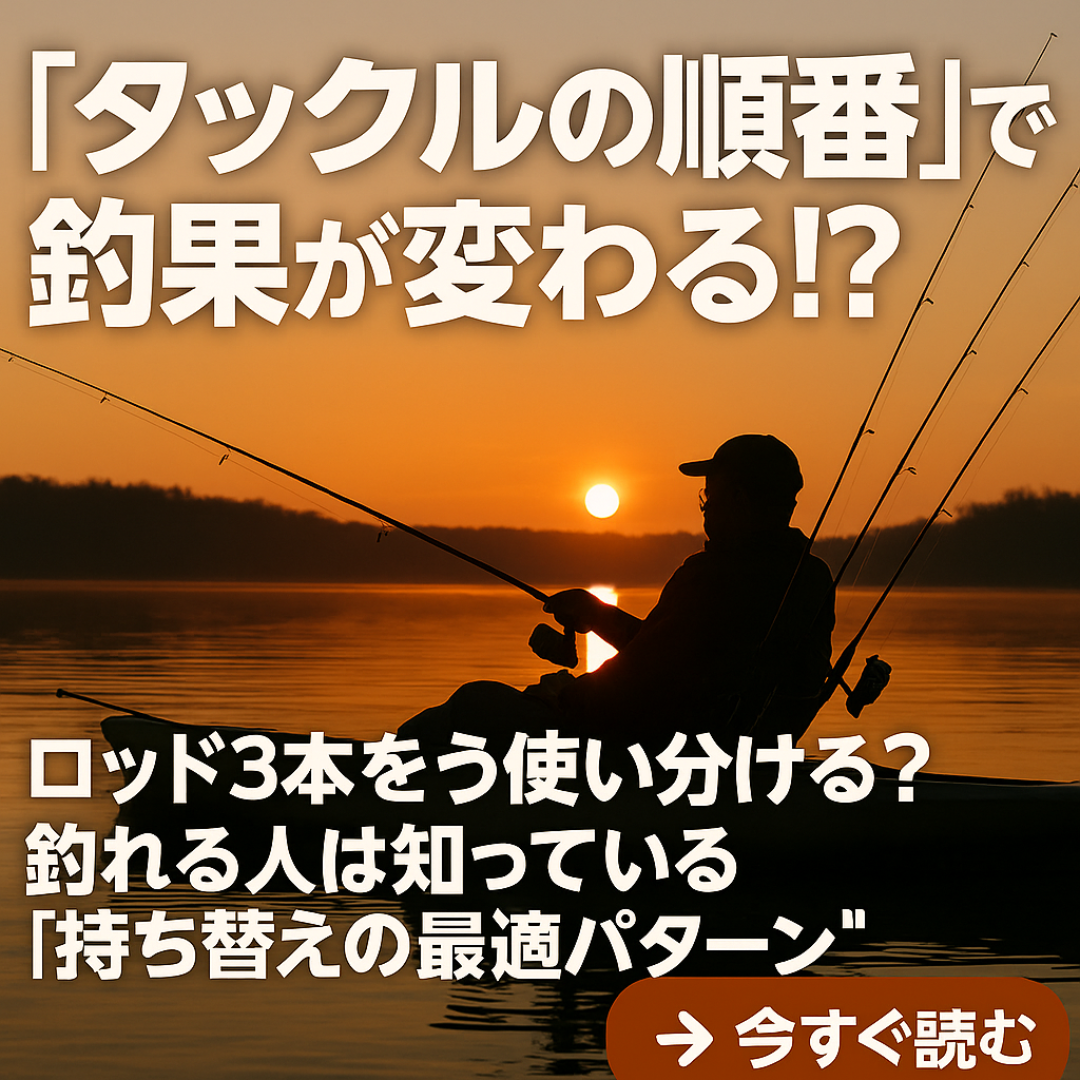「タックルの順番」で魚が釣れる?
ロッド3本持ち替えの最適パターン
◆ 朝イチ、いきなり選択を迫られる
カヤックを浮かべ、魚探のスイッチを入れてから5分後。
ベイト反応は悪くない。
でも、なぜか魚が浮いてない。潮もそこまで走っていない。
「さて、何から投げるか?」
この瞬間、3本のロッドがこちらをじっと見てくるような錯覚すらあります。
-
一本はタイラバ
-
一本はスピニングのジグ用
-
一本はキャスティング用のミノーやトップ
この3本を、どんな順番で使っていくか。
これが案外、1日の釣果を大きく左右するという話を、今日はしたいのです。
◆ “その時の1本”を最初に投げると失敗することがある
経験上、一番釣れそうなルアーを最初に投げてはいけない時があるんです。
たとえば朝のタイミング。
潮も緩いし、まだ日が差し込んでいない。
「こんなときはスロー系だろう」とタイラバから始めたくなる。
でも、その時、魚は浮いているだけで口を使うモードじゃないことがある。
すると、いきなり“食わせの武器”を消耗してしまい、
後の時間帯で使いどころを失ってしまう。
むしろ、最初は**「とりあえず魚にルアーを見せるだけ」**の一本を選んだほうがよかったりするのです。
◆ 実際に使っている3本のタックル構成
僕がよくやる3本体制はこんな感じです。
①【探る用】スピニング × 40g前後のジグ
-
ロングキャスト&ワイドに探れる
-
高活性の青物がいればすぐ出る
②【食わせ用】タイラバ × ベイトタックル
-
中層~底をじっくり攻める
-
反応が出たときに真価を発揮
③【リアクション用】キャスティング × シンペン or ミノー
-
表層~中層で反射食いを誘う
-
ナブラ撃ちやボイル対応にも強い
この3本を、状況に応じて“持ち替える順番”を調整していくのがキモです。
◆ 最初の1本は“場を読む道具”として使う
よく釣れる道具=最初に使うべき道具、ではありません。
むしろ、最初の1本は「今日の海の機嫌を探る」ための道具です。
-
水面に反応があるか?
-
中層に魚影があるか?
-
底を取りやすいか?
これを探るには、ジグが圧倒的に優秀。
フォールも効くし、巻きスピードでも反応の質が分かる。
仮にバイトがなくても、「この海域には何がいて、どう動いているか」を感じ取れます。
◆ 2本目で“確信に迫る”
ジグで反応がなかったら、次はタイラバでじっくりボトムレンジをトレースします。
タイラバの巻き上げスピードを少しずつ変えながら、
リフト&フォール気味に動かしたり、リーリングを止めてみたりする。
ここで食えば、もう**“その日”のパターンが確定**します。
逆に、ジグでもタイラバでも無反応だった場合、
「魚はいるけど口を使わない」というややこしい状態。
そこで出番なのが、キャスティングのリアクションベイトです。
◆ 3本目の“スイッチ”が釣果を左右する
魚って、じっくり見せたルアーはスルーして、
反射的に動くものに“思わず”食いつくことがあります。
つまり、最後の1本で“スイッチを入れる”役割を果たせるかが勝負。
僕がよく使うのは、
-
シンキングペンシルでのジャーキング
-
ミノーでの“逃げるアクション”
-
トップでのドッグウォーク(風が穏やかなら)
これを潮目やストラクチャー横で打つと、「ガツン!」と反応が出ることがあります。
◆ 順番が逆だと、チャンスを潰すこともある
ここで重要なのが、この順番を間違えると、魚にプレッシャーを与えてしまうということ。
たとえば、最初にリアクション系で派手に動かしてしまうと、
スレた魚が身を隠してしまい、そのあとタイラバやジグを通しても食わない。
これ、よくあります。
「ナブラ撃ったら終わった」みたいなパターンです。
だからこそ、探る→食わせる→スイッチを入れるという順序が非常に大事なんです。
◆ 「順番を考えること」自体が釣果につながる
釣りって、「何を使うか」が全てじゃないんですよね。
「いつ」「どの順番で」使うかで、まるで違う結果になる。
ロッド3本、いつも同じ構成でも、
その日の“回し方”ひとつで釣果がガラッと変わります。
そしてこの「順番」って、やっているうちに体に染みついてくる感覚でもあります。
◆ 経験でしか得られない“順番の組み立て”
結局、最適な順番は「これが正解」というより、その人の経験と場所、魚種によって違うんです。
でもひとつ確かなのは、
**「なんとなく投げてるうちは釣れない」**ということ。
「このロッドを使ったら、次はこれ」
「この反応なら、次はこのルアー」
そんな仮説と検証の繰り返しが、釣果に直結する。
だから、ロッドは3本がちょうどいい。
“選択肢がある”ということ自体が、釣りを有利にする。